ところで、この頃、国中の各地の動きは、どのようになっていたであろうか。
先日のクスコでのトゥパク・アマルの演説によって、彼らの皇帝の健在を知った国中のインカの民たちは、再び命を吹き返したように勢いづいていた。
かつてトゥパク・アマルがアレッチェに囚われた際には、著しく鎮圧化され、もはや風前の灯かとも見えた革命の火種ではあった。
だが、実際には、いかなる状況下にあろうとも、その火種は、インカの民たちの間で常に消えることなく燻(くすぶ)り続けていたのだった。
その背景には、トゥパク・アマルが獄中に繋がれていた間でさえも屈することなく、皇子マリアノを匿(かくま)いながら、隣国で覇権を広げ続けたアンドレスやアパサらの存在と功績が少なからずあったのだが。
いずれにしろ、トゥパク・アマルがクスコで久方ぶりの演説をぶったあの日、処刑寸前とまで言われていた彼が不死鳥の如く甦ったことは、民たちの間に燻っていた火種に、たっぷりと油を注いだも同然であった。
現在も、インカ軍幹部たちは、スペイン軍の強靭な武力と兵力を分散させるために、可能な限り多くの遠隔地まで、計略的に戦火を広げんと図っていた。

彼らは、あらかじめ的を絞った要衝の地へとインカ軍の有能な将と兵力、物資等を送り込み、戦闘準備を整えた上で、当地の同盟者や民衆たちと共に、領土奪還と彼らの復権を賭けて、戦端を一つ一つ着実に開いていった。
そして、英国艦隊との決戦に向けてトゥパク・アマルが沿岸線に下っている今、それらの具体的な采配を振っていたのは、全軍の中枢たる本陣にて夫の留守をあずかる彼の妻ミカエラ・バスティーダス、そして、老練の重臣ベルムデスである。
なお、かつて壮絶な死闘の末、最初の本拠地トゥンガスカの本陣を敵軍に奪われていたインカ軍は、彼らが初期の頃より奪還を果たしていた山岳の要衝地サンガララに、現在はその本陣を据えていた。
その地を全軍の司令塔として、ミカエラたちはスペイン軍を翻弄するかのように各地の反乱の火蓋を開いたり閉じたりしながら、トゥパク・アマルの復活以来、再び続々とインカ軍へ馳せ参じる義勇兵たちを迎え入れ、必要な地へと派兵していった。
そのような彼らの元に、見知らぬスペイン人が尋ねて来ましたと衛兵が取り次いで来たのは、少々時を遡るが、ちょうど海上では、フロレスたちスペイン艦隊と英国艦隊が激しい戦火を交えんとしている頃であった。

その頃、ミカエラとベルムデスは本部のテーブルに座し、地勢図を広げながら、次なる蜂起の場所を慎重に検討しているところであった。
「ミカエラ様、ベルムデス様、失礼いたします。
見知らぬスペイン人がお目通りを願い出て参っておりますが」
「面識の無いスペイン人が、このような時に我々に会いに来ようとは、一体、何用か?」
地勢図から顔を上げた麗しいミカエラの面差しは、トゥパク・アマルの代理たる過大な責任を背負いながらも、己の才覚を存分に発揮する立場を得て、いっそう輝きを増している。
「はっ!」と、衛兵はミカエラたちの方へと恭しく礼を払うと、「なんでも、トゥパク・アマル様からの書状を携えていると申しております」と、付け加えた。
「夫からの書状を?」
ミカエラとベルムデスは、瞬間、互いの顔を突き合わす。
それから、ミカエラが再び兵へ向いた。
「確かに、あの人の筆跡なのですか?」
「はっ、ミカエラ様!
間違いなくトゥパク・アマル様からの書状と思われます」
「その者の名は?」
「シモン、と申しております。
武器は携えておりませんが、眼光の鋭い、かなり身なりのいい男で、火急で重要な用向きと言っておりますが…」
暫しの間、ミカエラは、その彫像のような横顔で凛と光る目を思慮深く細めていたが、やがて「わかりました」と頷いた。
「会いましょう。
ここへお連れしてちょうだい」
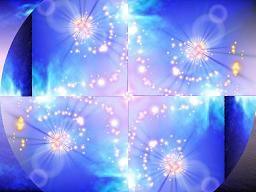
まもなく、ミカエラとベルムデスのいる天幕へと、衛兵に案内されてきたシモンが姿を現した。
ミカエラたちに危害を加えぬ証しのためであろう、彼は武器を携えてはいなかったが、明らかに戦さに臨まんとする戦闘服に身を包んでいる。
彼は入口の垂れ布をめくって中に足を踏み入れると、テーブルごしに隙無くこちらを凝視しているミカエラとベルムデスの方へと敏捷に礼を払った。
それから、その精気漲る精悍な面差しを上げ、奥の二人を真っ直ぐに見た。
いかにも慧眼の鋭そうな老練の重臣、そして、その傍に座し、射るような視線を放っている長身の女性がいる。
彼女は、曲線美も麗しい滑らかな肢体に、義勇兵の女性たちと同じ質素な素材から成る裾長の衣を身に着け、豊かな黒髪を形の良い頭部にゆったりと巻き上げていた。

決して豪華な装束を纏わずとも、ただならぬ風格を放つ二人――しかしながら、そのような二人を前にしても、一向に臆することなく、極めて沈着な太い声音でシモンが言う。
「お目にかかれて光栄です。
ミカエラ・バスティーダス殿。
そして、そちらは、トゥパク・アマル殿の腹心ベルムデス殿とお見受けいたします」
突然現れた見知らぬスペイン人、しかも、妙に落ち着き払ったその態度に、ミカエラもベルムデスも暫し返す反応に窮していたが、やがてベルムデスが静かな物腰で立ち上がった。
彼はシモンが危険な行為に及ぶことの無きよう鋭敏に目配りしながらも、温厚な口調で応ずる。
「いかにも、わたしはトゥパク・アマル様の側近の一人、ベルムデスでございます。
そして、こちらにおわしますお方は、トゥパク・アマル様の奥方ミカエラ様でございます。
シモン殿、と申しましたかな?
このような山奥の地まで、良くぞお越しくだされました。
さあ、どうぞ、こちらまでお入りなされませ」
シモンは、もう一礼を返すと、堂々とした足取りでミカエラの前に歩み出て、懐から一通の書状を取り出した。
そして、スッと相手の前へそれを差し出す。
「内容的には、さしたるものではありませんが、わたしがあなた方の敵ではないことをトゥパク・アマル殿にしたためてもらった書状です。
先日、彼と面会した際の経緯が書かれています。
今は互いに一刻も惜しい時なれば、目を通して頂ければ話も早いかと」
「トゥパクに会ったのですか?
このような非常時に、あの人も、そなたのような見も知らぬスペイン人との面会なぞ、良くおこなったものですね」
不審の念を全く隠そうともしないミカエラの物言いに、だが、シモンは相変わらず微塵も動ずることなく、自らミカエラの正面に腰を下ろすと書状を相手の目の前に置いた。
「読んで頂ければ分かります」
「…――」
やむなくミカエラはトゥパク・アマルからの書状を手に取ると、スラリと細い指先を端正な額に添え、長い睫毛を伏せながら、流れるような視線を紙面に走らせはじめた。

一方、そのような何気ない仕草さえも実に優美で、まるで絵画から抜け出してきたかのような美貌のミカエラを直近にして、己に対する剣のある言葉や態度にもかかわらず、さすがのシモンも思わず目を奪われている。
そんな彼の方に、ミカエラの脇のベルムデスが小さく咳払いをした。
ハッとシモンが我に返った時、ミカエラは一通り書状を読み終え、それをベルムデスに渡しているところであった。
受取った書状をベルムデスが目を通している間も、ミカエラは伏し目がちになった視線を机上に落としたまま、思い出しかけた何かを引き出そうとするかのように額を強く押さえている。
そんな彼女の脳裏に、もう大分前の軍議の席で、トゥパク・アマルが側近たちと交わしていた一連のやり取りが次第に甦ってきた。

『トゥパク・アマル様、クスコの奪還は不可欠ですが、植民地支配体制の瓦解ともなると、あやつらの巣窟である首府リマを放置とはいきますまい』
そう切り出したディエゴの言葉に、『うむ』と、トゥパク・アマルも深く頷いた。
『確かに、かの地は、植民地支配を崩壊させるためには、必ずや陥落させねばならぬ場所。
だが、スペイン側の勢力が非常に強く、さすがに手を出しづらい。
クリオーリョ(植民地生まれの白人)の者たちの協力が得られれば、ありがたいのだが……』
『そのご様子だと、トゥパク・アマル様、何か、お心当たりがおありですな?』
『無いことも、無い、が――まだ、決定的ではない』
トゥパク・アマルは沈着な声でそう言うと、傍らにあった革細工の書類箱から、厚い書状の束を取り出した。
『それは?!』
側近たちが身を乗り出す中、トゥパク・アマルは、それらの書状を広げ、隠し立て無く周囲の者たちに閲覧を許しながら続けていった。
『これは、わたしと親交の深いクスコの酒場のマスターが、そこに集い来るクリオーリョの革命分子たちの様子を書き記し、折々にわたしの元に送り届けてくれたものだ。
書状にある通り、だいぶ前から、我々の戦さにも関心を示している』
『しかし、トゥパク・アマル様』
ディエゴの太く強靭な指先が、書状の中の一部を、ぐっ、となぞった。
『この白人たちは、たとえ植民地体制が崩壊しようとも、あなた様がインカ皇帝として立たれることには、強い抵抗感を持っているようですが』
『そうようだな……』
トゥパク・アマルは、やや前傾姿勢になっていたその身をゆるやかに正すと、ディエゴを、そして、やはりディエゴと同じ眼差しで真剣に己に見入る周囲の者たちを、鋭くも、深く包み込むように見渡した。
『インカ帝国やインカ皇帝の復活を願うそなたたちの心は、とても嬉しく思っている。
かつて、この地に栄えた我らの帝国と我らの祖先のことを思えば、わたしとて、その思いが無いとは言えない。
だが、我々が此度の戦さを起こしたのは、このインカの地に生きる全ての民を、非道なる植民地支配体制の鎖から解放するため――そのことが叶うならば、我らに、それ以上の望みは持てぬであろう。
時は移り、今や、この国には、白人や黒人などインカ族以外の民も多く住み、その者たちの子孫も、我らと同じくこの国を祖国としている。
この地に生きる全ての民が真に共存していくために、そして、新たな時代の中でこの国が独立国家として生き延びていくために、必要な変革は受け入れていかねばなるまい。
わたしの言いたきことを、そなたたちならば、分かってくれるね?』

(あの時、あなたが言ってた人物が、今、わたくしの目の前にいるこの者なのですか?)
かつての一連のやり取りをハッキリと思い出したミカエラは、一旦、きつく瞼を閉じた。
それから、決然とその目を見開く。
「シモン殿」
今、己の方へと真っ直ぐに向けられたミカエラの瞳は、磨き上げられた黒曜石のように美しくも、強靭な戦士のように隙無く、鋭い。
不意に、ビョウと唸りながら強風が外を通り過ぎ、天幕の隙間から外気が流れ込んだ。
初夏の日中とはいえ、このサンガララの高地では、大気も風も、まだ身を切るような冷たさである。

「シモン殿、夫は、そなたとの面会を行った経緯と、それから、そなたに力を貸すようにと書状にしたためてきました。
つまりは、そなたは、スペイン人でありながらも――いえ、むしろ、見たところ上流階級に属するスペイン人にもかかわらず、この国の転覆を目論んでいるということなのね」
「転覆、という響きは少々物騒ですが、要するに植民地支配体制の瓦解という我々の目的は同じです。
インカ族のあなた方も、この国で生まれた白人の我々も、生まれがこの地であったというだけで、スペイン渡来の白人たちに不当な目に合わされてきた立場は同じ。
人種を問わず、同じ目的を持つ者同士が力を合わせるのは、理にかなっている。
それに、そのことは、トゥパク・アマル殿やあなた方が、この反乱のはじめから言い続けてきたことです。
今さら、わたしがクドクド説明する方が、おこがましいかと」
ミカエラが何かを言い返そうと唇を開きかけたが、それに構わず、シモンはさらに言葉を継いだ。
「それに、わたしが貧しいスペイン人ではないからといって、この現状に疑義を唱えてはいけないという決まりもありますまい。
それは、トゥパク・アマル殿や、ミカエラ殿あなた自身にも、当てはまることではありませんか?」
「……――」
思わず言葉を呑み込んだミカエラの脇で、平素と変わらぬ温厚なたたずまいのまま、ベルムデスが静かに二人のやり取りを見守っている。
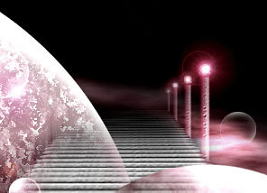
「ミカエラ殿、そもそも、いかに植民地下にあろうとも、あなた方はインカ族とはいえ、インカ皇族の末裔として特権階級にあったはずです。
このような反乱など起こさなくても、いや、むしろ、このような反乱など起こしさえしなければ、一生涯、肥沃な土地の領主として、何不自由無く暮らせるほどの地位も財産も、あなた方には保障されていたはずではありませんか」
そう言いながら懐から銀細工の葉巻入れを取り出したシモンは、「吸っても?」と、ミカエラたちに目配せする。
ミカエラがチラリと奥に控えていたインカ兵に頷くと、兵は棚から天然石の灰皿を下ろして素早くシモンの傍に置いた。
(年若くも見えるが、妙に貫禄もある。
一体、この者は何者なのか――?)
シモンが葉巻にゆっくりと火をつける動作を眺めやりながら、ミカエラは冷然とした面差しのまま、長い衣服の裾から僅かにのぞく美脚を組みなおす。

「そなたのことをもう少し教えてくださらない?
どう判断したらよいのか、正直、わたくしも迷っているのです」
「話すほどのこともないが、わたしのことをもう少しあなたが信用してくれる助けになるのなら」
低くそう言って、シモンは深く煙を吸い込んだ。
「わたしはこの新大陸の出身ですが、両親はスペイン人。
その両親も、わたしが幼い頃に亡くなっています。
ですが、幸い両親は新大陸きっての資産家だったおかげで、わたしは何の不自由も無く暮らしてくることができました。
両親は広大な農園やら鉱山やらをいろいろ残してくれましてね、まあ、要するに、同じスペイン人でさえ生活に窮々としていたこの時代のこの国にあって、わたしは、たいそう恵まれた環境にあったというわけです。

それも、たまたま、そうした裕福な家に生まれてきたというだけの理由で、です。
それは、インカ族とはいえ、今の時代でも特権階級にあったあなた方も、同じようなものだったのではないですか?
いえ、へんな意味ではなく、余裕があった分、かえって全体を良く見通せる境遇にあったという点で、です」
一旦、言葉を切ってミカエラたちの方を軽く見やると、シモンは、そのまま視線をスッとテーブル上に落とした。
その場の誰もが動きを止めている中で、ただ彼の葉巻の煙だけが、隙間風に煽られ揺らめいている。
やがて、天幕の中に、再びシモンの声が聞こえてくる。
「10代後半には、スペインにいた叔父を頼って、海の向こうに渡ったこともあります。
代々わたしの祖先が暮らしてきたスペインの大地を踏みしめ、感じ入るものも少なからずあったが、わたしは、もっと世界を見たかった。
当時から革命への思いを密かに胸に抱いていたわたしは、啓蒙思想を学ぶために、フランスに渡ったりもしました。
フランスは確かに興味深いところだったが、それでも、そう時の経たぬうちに再びスペインに戻ってきたのです。
何故なら……」
そこまで言うと、彼にしては珍しく躊躇(ためら)いがちに視線を泳がせ、ふと、天幕奥の小棚の上に飾られた陶の花瓶に目を留めた。
このような高地の戦場にもかかわらずミカエラが生けたのだろうか、雛菊に似た赤や黄や白色の可憐な花たちが、張り詰めた空間に潤いを添えている。

それらの花々を背にしながら、ミカエラが話の先を視線で促す。
シモンは花に目をやったまま、やや擦れた声でポツリと言った。
「このわたしが、柄にもなく、スペインを訪れたばかりの頃に出会ったスペイン人女性と恋に落ちていたのですよ」
「え…?」
「フランスで遊学中も彼女のことを忘れられず、またスペインに戻ってきたのです。
つまり、彼女に会うために」
「……」
思いもかけぬ話の流れに、ミカエラもベルムデスも戸惑いながら目を瞬かせた。
「フランスからスペインに戻って彼女と再会を果たしたわたしは、そこで結婚をしました。
当時、まだ20歳そこそこの若輩ではありましたが、わたしは彼女のことを真剣に愛していた。
今思えば、夢のような日々だった…。

そして、結婚した後、わたしにとっての真の祖国であるこの新大陸に、彼女を連れて戻って来たのです。
だが、この地に暮らして1年も経たぬうちに、ここの厳しい気候に耐えられなかった彼女は、風土病にかかり――あっけなくこの世を去ってしまった」
「――……」
微かに揺れはじめたミカエラの視界の中で、シモンはテーブル上で拳をきつく握り締めた。
まだ彼の手の中にあった葉巻の煙が、ゆっくりと巻き返りながら天井の方へと漂っていく。
「妻を失った辛さから、この地にいることに耐えられず、再びヨーロッパに戻っりもしたが、やはり、わたしにとっては、この国が祖国。
結局は、またこの地に帰ってきたというわけです」
「シモン殿…」
「まあ、そんなこんなのあれこれも、もう、暫く前のことだから、今さら感傷になど浸ってはいないが。
だが、妻を亡くしてから、わたしは失うものなど何も無くなった。

そんな折に、トゥパク・アマル殿やあなた方の此度の反乱が勃発したのです。
いつしかわたしの元に集うようになっていたクリオーリョ(当地生まれの白人)の革命分子たちも、あなた方に大いに刺激を受け、革命への機運はいっそう高まっています。
今、わたしは、己自身も財力も全てを投入できる場所を見出し、実に本望というわけです」
「…――そ」
ついシモンの話に引き込まれて聞き入ってしまっていた己を慌てて取り戻し、そのような内面を押し隠すようにして夫からの書状を忙しく折りたたみながら、ミカエラが問い返す。
「そ、それで?
そなたは、わたくしに何をしてほしいと?」
やっと本題に入れるかと、シモンは口元から葉巻をはずして姿勢を整えた。
「あなたに通行証を出して頂きたい。
今やインカ軍の占拠した地は、あなたの発行した通行証が無ければ通行することができません。
これからわたしはリマに進軍するつもりですが、この数日で予想以上に各地のインカ軍の蜂起が多発し、今となっては、通行証無くば、リマまで到達することは至難です。
わたし一人ならば、すり抜けていくこともできそうな場所でも、多人数を率いてともなると、さすがにそういうわけにもいきますまい」

「リマへ……!」
ミカエラとベルムデスは共に、無意識のうちに、にわかに居住まいを正した。
「そう、リマです。
あそこは白人たちの巣窟だ。
インカ族のあなた方では、なかなか手を伸ばしにくい場所でしょう。
そこに、わたしが兵を進める。
あなた方にとっても、悪い話ではないと思うが」
ミカエラたちの様子に微かに笑みを浮かべながら、シモンが葉巻を悠然とくゆらせる。
「それに、道中、街々を抜けながら、有志の白人兵を募って増兵もしたい。
あなた方が呼びかけても参戦を躊躇っていた白人たちの中にも、現状に不満を抱いている者たちは少なからずおりましょう。

同じ白人であるわたしが直接声をかければ、動こうとする者たちもいるはずです。
こちらとしても、あなた方の息がかかった土地ならば、何かと事を進めやすいですしね」
そろそろ話しが通るかと算段しながら、トッと、葉巻を灰皿に打ち付けたシモンの耳に、冷ややかなほどピシャリとした口調でミカエラの声が響く。
「だけど、そなたを本当に信用して良いのかしら?
そなたがスペイン軍と通じていないという証拠は?」
「やれやれ、まだ、わたしを疑うのですか?」
シモンは煙を吐きながら、小さく息をついた。
「一体、どうしたら、わたしを信じてくれると言うのですか?
そのために、わたしの生い立ちや結婚話しまでしたではありませんか。
それに、あなたのご主人だって、わたしを信用してくれたのだが。
そもそも、その書状はそのための――」
「話をそらさないで。
大事なことなのですから」
艶やかな長い睫毛に縁取られた険しい瞳をシモンに据えたまま、有無を言わせぬ厳しさでミカエラが短く言い放った。
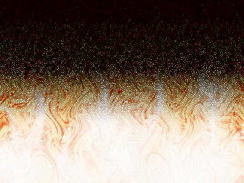
そんな彼女の態度に、シモンは葉巻を灰皿に擦り付けて消し去りながら、フゥッと、再び深く煙を吐く。
それから、暫しの間、彼は椅子に身を投げ出すようにもたれたまま、思案顔で顎をかいていた。
が、やがて、何か思うところありげに、おもむろに身を起こす。
「噂には聞いていたが、あなたは、なかなか手厳しい人だ。
ミカエラ殿」
「なっ……!」
ミカエラが咄嗟に何かを言い返そうと身を乗り出したところを、シモンは素早く腕を上げて制した。
それから、厚い胸板を僅かに反らし、真正面から相手に向き直る。
「証明などできない。
だが、ならば、ひとつ警告を」
「警告?」

他方、そのようなミカエラとシモンのやり取りを見守る老賢なベルムデスの眼差しが、いっそう力を帯びて眼前の白人に注がれる。
ベルムデスの目の中で、シモンは、テーブル上に広げられたままだった地勢図を引き寄せた。
そして、ペルー沖を指先でなぞりながら、太く沈着な声音でゆっくりと語り出す。
「今頃は、洋上で英国艦隊とスペイン艦隊が激突しているはずです。
英国艦隊を率いるジョンストンとパリアは歴戦の強者(つわもの)、対するスペイン艦隊を率いるのは腑抜けのベルナルド、そして、フロレス。
フロレスは陸上戦ではそれなりの指揮官として鳴らしていたが、海戦では所詮は素人です。
恐らく、英国艦隊の敵とはなりますまい。
第一、 戦艦の性能そのものに差が大きい。
詰まるところ、英国艦隊がスペイン艦隊を撃破するのは時間の問題であって、その間、あなた方インカ軍は両者が最大限に消耗させ合うのを念じながら、高みの見物というわけだ」
そう言って、シモンは懐の葉巻入れから、また新たな葉巻を抜き取って口にくわえ、ミカエラに一瞥を投げた。

その視線の先で、ミカエラは、形良くスッと通った細い眉を一筋も動かすことなく、ただ冷ややかに目を細める。
「それで?」
一方、シモンは葉巻に火をつけ僅かに微笑すると、銀色に光る葉巻入れの角で沿岸線を、コッ、コッ、と叩いた。
「スペイン艦隊を破った英国艦隊は、次は、このペルー沿岸に攻め寄せてくることになる。
もし英国艦隊が、スペイン軍の軍港とあの堅固な砦を制圧し、その上、首尾よくトゥパク・アマル殿やアレッチェを葬り去るか捕虜にできれば、彼らはインカ軍やスペイン軍に降伏を迫ることができる。
あるいは、彼らが、あなた方の激しい抵抗にあったとしても、そこまで段取りをつけることができた後であれば、彼らの軍艦とあの砦を拠点に粘りながら、英国本土から多数の増援部隊を早急に呼び寄せるに違いない。
そうなってからでは、あなた方の勝機は、まず厳しい」

先刻から、天幕の外でさらに強まった外気が、しきりに内部に流れ込んでいる。
風に煽られハラリと落ちかかった己の前髪を、ミカエラの指先が鋭い手つきで梳きあげた。
「そのようなことは、そなたに言われずとも分かっています。
そうならぬために、わたくしたちは、あらん限りの手を尽くそうとしているのですから」
シモンは流れ来る冷風を顔に吹きまつわらせながら、相変わらず感情の揺らぎのない口調で泰然と答える。
「もちろん、わたしが言いたいのは、そんなことではありません」
その時、不意に天幕入り口の垂れ布が大きく翻り、大量の冷気と共に眩い陽光が天幕の奥までサァッと射し込んだ。
突風の仕業にしては激しすぎると、反射的に内部の三人がそちらを振り向くと、そこには一人のインカ族の少年が立っていた。
色褪せた古布を紡ぎ合わせたような義勇兵と同じ戦闘衣に簡素な皮製のポンチョを羽織り、インカの少年らしく肩口辺りで切り揃えられた黒髪が絹糸のようにサラサラと風の中で揺れている。
そして、その腰には、その身なりにしては、ずいぶん重厚な剣が提げられていた。

「イポーリト…!
どうしたのです。
今は大事な話し合いの最中なのですよ」
たしなめるようなミカエラの言葉に、シモンはハッとして、改めて少年をまじまじと見た。
イポーリト――もちろん、シモンもその名前は知っていた。
トゥパク・アマルとミカエラの第一子であり、時が時であれば、トゥパク・アマルの後を継ぐ皇位継承者であったかもしれない人物だ。
「すいません、母上。
表にたいそう立派な馬が繋がれていたものだから。
衛兵に尋ねたら、見も知らぬスペイン人のお客人が突然やってきたのだと聞いて。
このような時に、そんな大胆なことをされるとは、一体、どんな人なのか会いたいと思って、衛兵に無理を言って通してもらったんです」
溌剌とした口調でキビキビと語ると、イポーリトは、その利発そうな眼差しを真っ直ぐシモンに向けた。
少年らしい好奇心に輝く切れ長の目はトゥパク・アマルに良く似ているが、端正で涼やかな全体的な風貌はミカエラにもとても良く似ている。

実年齢はまだ12〜13歳のはずだが、シモンの目にはもっと大分年上に見えて、少年というよりも青年という方が相応しい雰囲気に思われた。
本来はまだ子どものような年だというのに、恐らく、早々に様々な辛苦を舐めさせられてきたためであろう。
実際、このイポーリトは、トゥパク・アマルやミカエラと共に――といっても、個々バラバラにだが――暗黒の地下牢に幽閉されていたこともあるのだ。
「イポーリト様、ささ、どうぞもっと奥までお入りくだされませ。
こちらのお方が、お客人のシモン様でございます」
すかさず起立して丁寧な礼を払ったベルムデスの姿につられるようにして、シモンも椅子から立ち上がった。
「お会いできて光栄です、イポーリト殿。
シモンです、よろしく」
そう言って右腕を差し出すと、イポーリトは闊達な足取りで彼の前に進み来て、その手を力強く握り返した。
そして、にっこりと優美に微笑む。
「イポーリトです、よろしくお願いします」

長身の両親に似て既に背丈もかなりあり、物怖じしない沈着な口調と気品ある物腰しとに、ますますシモンは相手の年齢を錯覚してしまいそうだった。
他方、そのような二人の様子に、ミカエラは困惑気味な表情を隠せない。
「息子さんがいても、わたしは一向にかまいませんが」
シモンはそう伝えると、少年に自分の隣の椅子を勧めた。
「ありがとうございます」とイポーリトは笑顔で応じ、そのままテーブル上を見渡して軽く肩を竦める。
「母上、お茶ぐらい出してさしあげたらいいのに」

そんな息子の方へミカエラが何かを言おうとするよりも早く、イポーリトは外の衛兵の方角へと一声かけ、それから面前に広げられた地勢図に目を留めた。
そして、隣のシモンを振り向き、礼を込めた改まった面持ちで言う。
「中断させてしまって、すいませんでした。
どうか話しの続きを」
「それでは」と言いつつも、シモンは軽く顔をうつむかせ、にわかに込み上げた微苦笑を噛み殺さずにはいられなかった。
(どちらかと言えば見かけは母親似だが、どうやら性格は父親似らしい。
それにしても……)
ミカエラの冷厳な態度には何の感情の揺れも覚えなかった己が、まだ年若い少年に僅かなりとも呑まれそうになったのが、自分で可笑しかったのだ。
ほどなく衛兵が湯気の立つ熱いコカ茶のカップを4つ持ってきて、丁重な物腰で配っていった。
コカ茶の甘く香ばしい匂いが天幕の中に立ち込めていく。
衛兵が立ち去ると、シモンは軽く咳払いしてから、やっと先程までの調子に戻って語りだした。
「イポーリト殿には話しの途中からになってしまうが、わたしはリマに進軍するにあたって、その通行証をミカエラ殿から頂きに来たのです。
先だって、トゥパク・アマル殿にも会ってきましたよ。
そこに書状もある」
「父上に?!」
イポーリトは若い瞳をいっそう大きく輝かせた。

それから、トゥパク・アマルの書状を大事そうに手にとって、そこに綴られている流麗な字体の上に褐色の指先を滑らせた。
「これは確かに父上の字だ。
でも、母上は簡単にはあなたを信用してはくれず、だから、あなたは母上を説得しようと色々と算段を巡らせている、そんなところですね?」
「まあ、そんなところです」
シモンは再び微苦笑を湛えて頷き、それから、ミカエラとベルムデスにも軽く視線を流した。
「さて、さっきから戦況をなぞってきた通り、英国側の思惑を打ち砕くために、沿岸に押し寄せた英国艦隊に対してスペイン軍陸上部隊がまず戦火を交え、時を見てトゥパク・アマル殿もそこに介入して三つ巴の乱戦へと突入する。
あわよくば、英国艦隊とスペイン軍が共(とも)食いし合う隙を突いて、両軍を叩き潰したいというのが、あなた方インカ軍の筋書きでしょう。

だが、如何に英国艦隊とペイン軍が互いに叩き合ってくれるとはいえ、最終的には両者を押さえ込まねばならないインカ軍に求められる武力や戦力とて、それこそ並大抵なものではありますまい。
主だったかなりの兵を沿岸部に投入せざるを得ないはずだ。
現に、わたしがトゥパク・アマル殿との面会に訪れた際、あの陣営で、アンドレス殿にも会いました」
父に似た切れ長の目を研ぎ澄ませて地勢図に目をやり、真剣に話しに聞き入っていたイポーリトが、パッと顔を上げた。
「アンドレスにも…!」
シモンは少年の方へとゆっくり頷いた。
「そのアンドレス殿と言えば、今では、トゥパク・アマル殿の片腕の一人でもありましょう。
彼の軍も、トゥパク・アマル殿と共に沿岸部隊に配属されている」
「シモン殿」
先刻からの持ってまわったシモンの話に、ミカエラなりに根気強く耳を傾け続けてきたものの、さすがに苛立ちの隠せぬ声で呻いた。
「だから、そなたは何を言いたいのです?
そろそろ話をまとめてくださらない?」
「これは失礼。
では、本題を。
ミカエラ殿、そして、イポーリト殿やベルムデス殿もですが、あなた方がスペイン軍の兵力を各地に分散させようと躍起になっているのと同じように、あのアレッチェも、インカ軍の兵力を限られた地域に縛り付けておこうと手ぐすね引いているかもしれませんよ?

しかも、あの男らしい、いろいろ良からぬ思惑を持って。
例えば――」
シモンは飄々たる口調を変えぬまま、再び地勢図をなぞるために僅かに身を乗り出す。
「例えば、トゥパク・アマル殿を嫌がらせるために、この瞬間も、アレッチェがことさら手を回してみたくなる場所はどことお思いか?」
他の三人の視線が己に集中するのを感じながら、彼は地勢図を見やりつつ、頤(おとがい)を擦った。
「互いに兵力が無尽蔵にあるわけではないですからね。
英国艦隊が洋上でスペイン艦隊を破れば、その後、沿岸線での両軍の戦いにトゥパク・アマル殿やアンドレス軍が介入する。
さらに、もっと全体的に眺めてみれば、今頃、クスコでは、ディエゴ殿のインカ軍精鋭部隊がスペイン軍の猛将バリェ将軍と激突中。
他の地域でも、インカ軍の同盟者たちが次々と蜂起しており、ついでに言えば、隣国ラ・プラタ副王領では、トゥパク・アマル殿の同盟者フリアン・アパサが、スペイン軍の手薄を突いてインカ側の占拠地を拡大中ときている。

勢い良く戦火が広がっているだけに、言ってみれば、皆、それぞれに手一杯な状態だ。
さて、では、この状況下で、今、インカ軍の最たる急所はどこか?」
地勢図を見下ろしていた精悍な面(おもて)を上げ、じっと己を見つめるシモンの精気溢れる眼光の前で、ミカエラは不覚にも固唾を呑んだ。
そのミカエラの脇では、重臣ベルムデスが既にシモンの言いたきことを察してか、沈着ながらも鋭利さを増した眼差しを、ひたとこちらに据えている。
そして、シモン自身の隣では、イポーリトが、漆黒の彫像の如く端正な横顔をひどく険しくして、地勢図の一箇所を睨みつけていた。
シモンは、前傾姿勢になっていたその身を椅子の背もたれへと戻すと、おもむろに頷く。
「そう。
もうお察しの通りです。
つまり、それは」
シモンの強靭な指先が、地勢図上の一点――この本陣の据えられたサンガララの地――を、真っ直ぐ指し示した。
「――!!」

不規則に微動する瞳を見開いて息を殺しているミカエラとイポーリトへ、そして、思慮深く瞼を細めているベルムデスへと、シモンはじんぐりに視線を動かした。
「当地にも、それ相応の精鋭の兵たちを配備してはいようが、他の戦場と比べると、重要な戦地に主だった将や兵を派兵してしまっている今、当地の守りは手薄と見受けられる。
そこに敵が目をつけぬはずはない。
増してや、ここには、トゥパク・アマル殿の妻であるミカエラ殿、あなたがいる。
そして、大事な皇子、イポーリト殿も」
イポーリトはグッと息を呑み、それから、いっそう険しさのいや増した表情で、唇を噛み締めた。
「あなたは、あのアレッチェが、母上や僕を狙っていると言うのですか?」
微かに動揺の気配を滲ませながらも、年端に似合わぬ毅然とした沈着な声である。
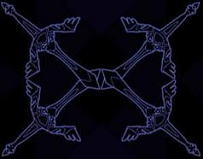
対するシモンは、「例えばの話です」と挟んでから、さらに言葉を継いだ。
「各地の戦場が激戦化した隙を突き、当地を襲ってあなた方のどちらかを捕らえ、人質として、トゥパク・アマル殿に降伏を迫る。
――いかにも、あの男の好きそうなやり方だ」
一方、ミカエラは、突如、弾かれたようにテーブルから立ち上がった。
そして、強く拳を握り締め、目元を険しく吊り上げ、シモンを睥睨する。
「そなたは、何を言い出すのです!!
わたくしやイポーリトが人質になったら、夫が降伏すると?!
この国家の重大事に、夫が私情を優先させるとでも言うのですか?!」
握り締めた拳を震わせているミカエラの肩を、ベルムデスが宥めるようにそっと抱き、椅子へと再び座らせる。
「ですから、あくまで例えばの話です」と、太く沈着に応え、シモンは新たな葉巻を葉巻入れから取り出しかけた。
が、己の方をじっと見つめている少年の存在を思い出してか、再び入れ物の中にそれを押し込んだ。
そして、やや手持ち無沙汰に、両の手を擦り合わせる。

「だが、絶対に無いといは言い切れまい?
実際、かつて、トゥパク・アマル殿は、クスコの牢から抜け出す際にも、あなた方を助け出して、共に脱獄を果たしている」
「それと、これと、どう関係があると言うのです?!」
激昂しているミカエラの前で、シモンは熱く香ばしいコカ茶をありがたそうにすすった。
それから、彼も、今度は真面目な面差しで、一語、一語、諭すように続けていく。
「地下牢での極限的な状況下で、あなた方まで助け出した――そのことに伴うリスクは、彼一人が脱出を試みるよりも遥かに甚大だったはずです。
それに、たとえ、あなた方を見捨てて彼だけが脱獄を果たしていたとしても、民衆だって、やむを得ぬ判断であったと同情こそすれ、彼を批判することはなかったはず。
あのトゥパク・アマル殿に、それやこれやが計算できないはずもない。
それでも、彼は、愛する家族を助け出す道を選んだ。
トゥパク・アマル殿が、ただ国家のことだけを考えていたのなら、そのようなことをしたでしょうか?
――もちろん、それが正解だったのか、否なのか、そんなことを論じるつもりは毛頭ありません。
だが、事実として、そういう人物なのですよ、彼は」
「――……!」

暫し継ぐ言葉も出ぬほどにその場に硬直していたミカエラに、テーブルごしにイポーリトがそっと手を差し伸べて、優しく母の腕に触れた。
「母上。
どうかお気を鎮めてください。
確かに、父上にはそういうところがあるし、この陣営の護りのことも、シモン殿の仰っていることには一理あるように僕は思います」
「イポーリト……!」
ミカエラは、シモンを睨みつけていた険しい横顔を、今度は、キッ、とイポーリトに向けた。
しかし、ほどなく氷が溶けるかのように、息子を見つめる黒曜石の瞳が大きく揺れはじめる。
ミカエラは、それを隠すようにして、長い睫毛をサッと伏せた。
やがて、再びシモンの声が静かに響くてくる。
「ミカエラ殿。
仮にあなたが言うように、人質に捕らえたあなた方と引き換えに、トゥパク・アマル殿が降伏まではしないとしましょう。
だが、それでも、もしそのような事態になれば、何らかの悪条件を彼が呑む可能性は十分にあると、あなたも思っているのではないですか?」
「…――」
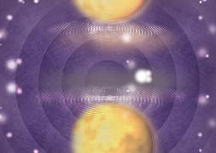
かなり長く感じられる沈黙の後、やがて、ミカエラの艶やかな唇が微かに動いた。
「そなたの警告、心に留め置きましょう、シモン殿。
人質の話はさておいても、当地が手薄であることは事実。
確かに、それは警戒に値する……」
それから、ミカエラは、ベルムデスの方へも視線を馳せて互いに頷き、今一度、シモンへと向き直った。
その表情には、既に凛とした平静さを取り戻している。
「シモン殿、そなたの要求、聞き届けましょう。
これからわたくしの用意する通行証を持って、急ぎリマへと向かわれるがよい。